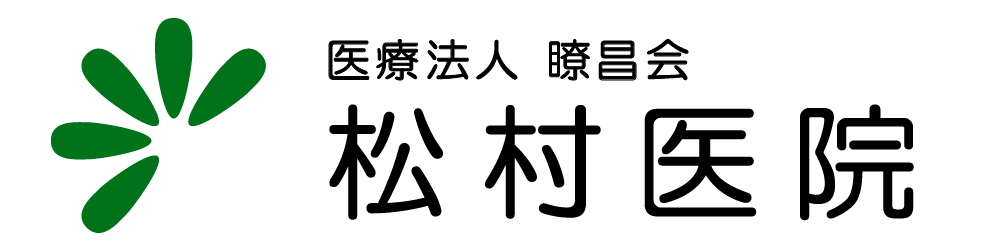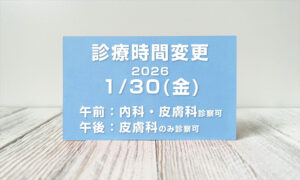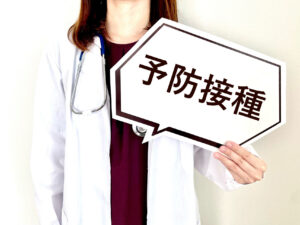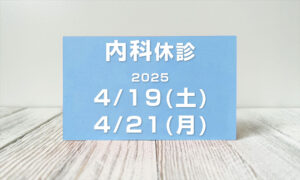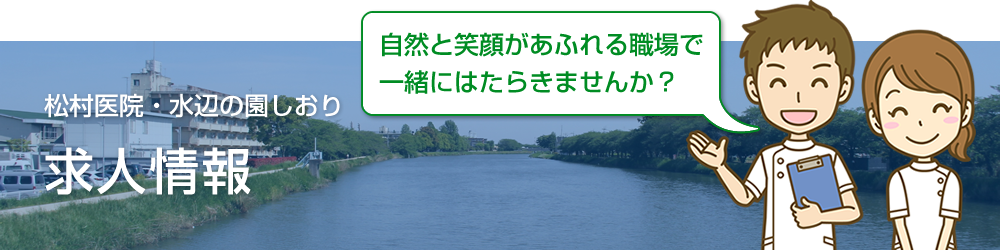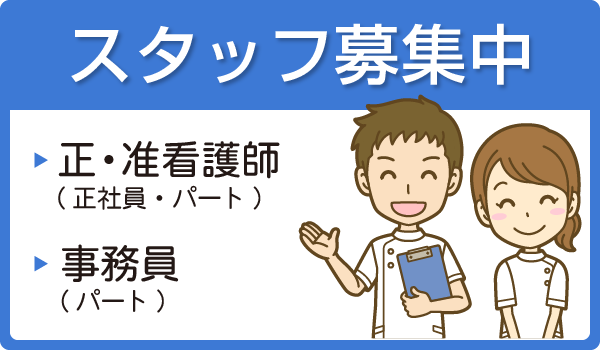
インフルエンザウイルスとは
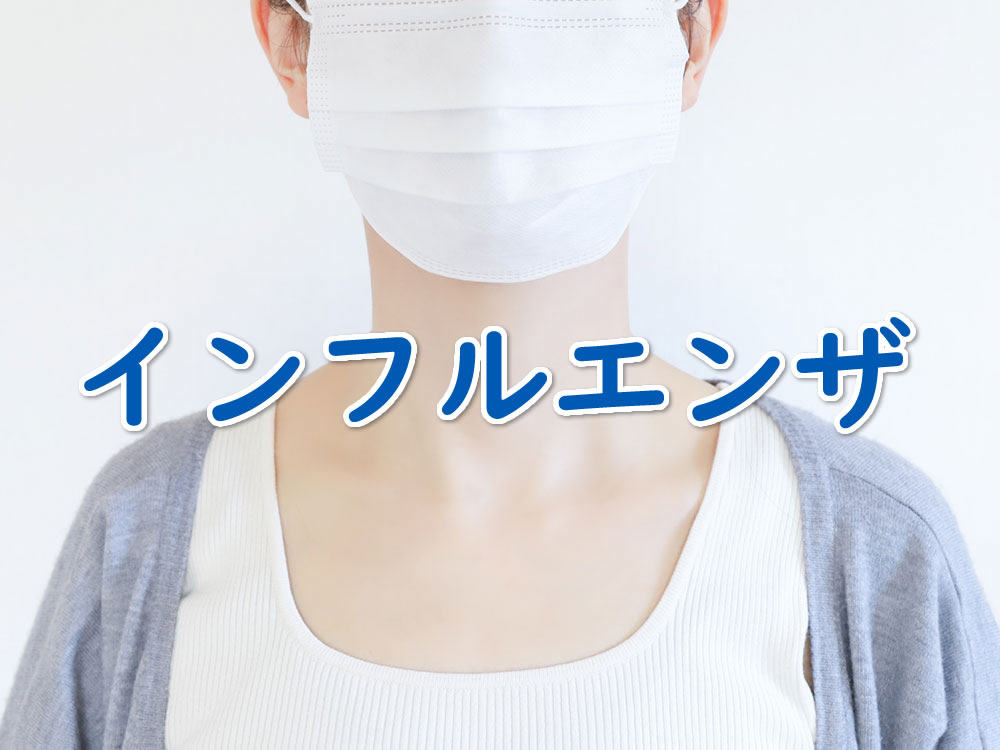
インフルエンザウイルスとは
インフルエンザはウイルスによる流行性の疾患で、ほぼ毎年流行を繰り返します。
いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が広がります。
日本では例年12月~3月ころに多く流行しますが、沖縄など亜熱帯地方では夏季にも流行することがあります。
インフルエンザウイルスには、ウイルス表面突起の抗原性によりA型、B型、C型があります。
C型は、稀に小児期に重症化することがありますが、成人では症状が軽く、あまり問題になりません。
インフルエンザの症状
インフルエンザは、普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳などの症状も見られます。
厚労省の感染症発生動向調査による症状診断基準では、下記の4項目すべてを満たすこと、となっています。
しかし、発熱が37℃台など全ての症状がそろわないこともあり(とくに高齢者の場合)、必ずしも症状はこの基準どおりではありません。
- 突然の発症
- 38度以上の発熱
- 上気道炎症状(咳、鼻水、咽頭痛)
- 全身症状(筋肉痛、全身倦怠など)
高齢者や体の弱っている方は、インフルエンザにかかることにより細菌にも感染しやすくなっています。
このため、細菌にも感染する(混合感染)ことによっておこる肺炎、気管支炎などの合併症にも注意が必要です。
高齢者の肺炎は頻度、致命率ともに決して低くはありません。
また、小児の脳症はまれですが、意識状態や行動に注意が必要です。
インフルエンザの診断
当院の外来において、15分以内で簡単にできる迅速診断法で、インフルエンザかどうか、さらにA型か、B型かを診断することが可能です。
ただ、この検査方法では、発病早期にはの鼻咽腔粘膜のウイルス量がまだ少ないため、陽性に出ない場合もあります。
インフルエンザの治療と副作用
オセルタミビル(商品名:タミフル・内服)、ザナビミル(商品名:リレンザ・吸入)、アマンタジン(商品名:シンメトレル・内服)という画期的な特効薬が保険適応です。
タミフルやリレンザを内服すると、発熱期間は通常1~2日間短縮されます(A型で30時間前後、B型で40~50時間)。
このため、解熱剤は殆どいらなくなりました。
発病からなるべく早い時期(12時間以内)、遅くても48時間内に内服すると、解熱までの時間が短縮され、ウイルス排泄量も減少し、きわめて有効です。
インフルエンザをはじめ、ウイルスには抗生剤は効きません。
しかし、高齢者や体の弱っている方の混合感染でおこる肺炎、気管支炎など、合併症に対する治療として抗菌薬を使用することもあります。
オセルタミビルの副作用は、投与した患者さんの1%程度にみられ、その内容は、下痢、腹痛、嘔気などでこのほか低体温、動悸、眠気、頭痛、不快感があります。
かつて「異常行動が見られた」、と報道されたことがありましたが、薬剤との因果関係は証明されていません。
いずれの抗インフルエンザ薬も安全性が高いといえますが、尚、1歳未満ではタミフルの安全性はまだ確立されていません。
2007年3月、タミフルについては厚生労働省の通達が下記の通りありました。
10歳以上の未成年の患者においては、因果関係は不明であるものの、本剤の服用後に異常行動を発現し、転落等の事故に至った例が報告されている。
このため、この年代の患者には、合併症、既往歴等からハイリスク患者と判断される場合を除いては、原則として本剤の使用を差し控えること。また、小児・未成年者については、万が一の事故を防止するための予防的な対応として、本剤による治療が開始された後は、①異常行動の発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場合、少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮すること。
なお、インフルエンザ脳症等によっても、同様の症状が現れるとの報告がある。
厚生労働省
家庭におけるインフルエンザ対策
流行前のワクチン接種
有効性と安全性の高いことが確認されています。
早期受診
早期に特効薬を内服することより、いち早く治すことが出来ます。
安静
過労、宴会、夜更かしなど無理をしないで安静が一番です。
からだの抵抗力を高めるために十分な休養と栄養を日ごろから心がけましょう
部屋の保温(22℃)と湿度維持(50-60%以上)
ウイルスは低温、乾燥を好み、乾燥のため気道粘膜を傷めないように、部屋の湿度を保つ工夫(濡れタオル、植木鉢など)をしましょう。
水分、ミネラル、ビタミンの補給
脱水を防ぎ、脳症、肺炎など重症化を防ぐためにも、これらを充分に補給しましょう。
家庭内・学校・職場内感染を防止
感染者からなるべく距離を置き、マスクなどで飛沫感染を防ぐ工夫も大切です。
一般的に、インフルエンザを発症してから3~7日間はウイルスを排出すると言われています。
ウイルスを排出している間は、患者は感染力があるといえます。
学校保健法では、「解熱した後2日を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています。
(ただし、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときはこの限りではありません)
インフルエンザの予防
ワクチンの効果
インフルエンザワクチンは世界的に広く用いられ、通常は不活化された抗原(ウイルス)が用いられます。
高齢者のインフルエンザ罹患による肺炎などの死亡率は高く、2001年から65歳以上の公的接種が開始されました。
65歳以上の高齢者、60~64歳で基礎疾患(心臓、腎臓、呼吸器、免疫不全など)を有する方、インフルエンザ発症と重症化を防ぎたい全ての方に勧められます。
ワクチンの抗原と、流行株の変異からくる抗原性のずれが発生し、必ずしも予防は万全ではありません。
しかし、予防接種を行うことにより、インフルエンザに罹りにくくし、罹っても肺炎など重症化が防げられることが期待でき、有効性と安全性が高いことも確認されています。
インフルエンザに対するワクチンは、個人差はありますが、その効果が現れるまでに通常約2週間程度かかり、約5ヶ月間その効果が持続するとされています。
日本でのインフルエンザの流行は12月下旬から3月上旬が中心になりますので、12月上旬までには接種をすまされることをお勧めします。
ワクチン接種の効果的回数については、基礎免疫の少ない15歳以下では原則2回接種が勧められます。
2回接種の場合は、2回目は1回目から1~4週間あけて接種しますので、1回目をさらに早めに接種しましょう。
ワクチン接種の副反応
数パーセントの人に起こり得ますが、注射した部位が一時的に赤くなる程度です。
発熱、倦怠感などの全身症状はまれです。
鶏卵、鶏肉にアレルギーのある方や、けいれんの既往のある方、などの接種は注意が必要です。ご相談ください。